
クリニックが譲渡成立するまでの期間は?【プロセスと具体的スケジュール】

クリニックの売却や譲渡を検討してから、第三者への譲渡が成立するまでの期間は、およそ2年前後が必要とされています。クリニックが譲渡成立する期間には、事前の相談はもちろんクリニックの将来性や収益性について実地で詳しく調査するほか、手続きや引き継ぎ業務など膨大な業務を進める必要があります。
譲渡に必要なプロセスを焦れば見落としも増え、後悔してしまうケースもあるため、慎重にじっくり時間をかけて進めましょう。当記事ではクリニックが譲渡成立する期間や、期間中にやるべきことについて解説します。
クリニック譲渡成立までのプロセス

クリニックが譲渡成立するまでには、さまざまな交渉手続きを進める必要があり、焦らず段階を踏んで進めていくことが大切です。ここではクリニック譲渡までに必要なプロセスを解説します。
事前相談・機密保持契約契約書締結
まずはクリニックや病院のM&Aを専門に扱っている仲介会社に事前相談します。交渉や手続きのサポートを専門的に、第三者視点からサポートしてもらえるため、親族や知人同士のクリニック譲渡であっても、仲介会社を利用しましょう。
クリニックの譲渡を検討していること、譲渡において譲れない条件を伝えたうえで、クリニック譲渡における具体的なプランを提案してもらえます。慎重にクリニック譲渡について検討するため、事前相談だけでも1〜2ヶ月かかる場合もあるでしょう。
M&Aのプロセスにおいて、初めに結ばれる契約は機密保持契約書であることが一般的です。「自社を譲渡したい」という意向を譲渡する側が示した際、譲渡する側は決算報告やその他の企業情報を提出することになります。この情報提供の段階で、双方が機密保持契約に署名するのです。
仲介契約書の締結
仲介契約書は、M&A仲介会社が引き受ける業務の範囲を明記した文書です。
クリニック譲渡における基本的な方針が固まり、さらに具体的に譲渡交渉することが決まったら、M&A仲介会社から譲渡サポートを受けるため、仲介契約書を締結します。
書類の作成
クリニック譲渡において必要な情報をまとめた書類であるノンネームシートを作成します。書類にはクリニックの病床数や導入設備の内容、希望する譲渡価格など、譲渡価格を検討するための情報を記載します。
ただし譲渡は実際に決まるまで公にしないことが基本です。譲渡したいクリニックの名称は隠して、買収を考えている医療法人にも具体的なクリニック名はわからないよう作成し、譲渡内容に興味を持ってもらえる医療法人を探します。
ネームクリア
ノンネームシートの内容に興味を持ち、具体的に譲渡契約を検討したいと考える医療法人や医師が見つかったら、機密保持契約を交わしてネームクリアします。ネームクリアとは自分の情報を明かすことを指し、ノンネームシートでは隠していたクリニック名や具体的な医師名を公開します。
実際に書類を作成し、ネームクリアまで進めるまでにはクリニックの条件によっても期間が変動し、1ヶ月以内で見つかる場合もあれば、1年以上かかる場合もあるでしょう。
トップ面談
ネームクリアして機密保持契約も交わしたら、譲渡したい側と買収したい側の院長や経営陣同士でトップ面談します。トップ面談ではクリニックの運営方針や譲渡における条件交渉、クリニック譲渡における医師確認を行います。
トップ面談は1日で終わる場合もあれば、複数回行う場合もあるため慎重に面談を進めましょう。
現地見学
面談が終わったら、譲渡クリニックの現地見学に進みます。クリニックの集客力や設備、スタッフが働く様子を目で見て確認するほか、資産価値のある設備内容についても確認できます。
規模の大きいであれば確認店も増えるため、現地見学は1回〜複数回に分けて行う場合もあるでしょう。もちろん現地見学したうえで、譲渡条件に合わなければ譲渡契約を断ることもできます。
条件交渉
面談と現地見学をふまえて、具体的な譲渡条件や譲渡価格を決めるため、条件交渉します。特にクリニック譲渡では譲渡する側は「高く売りたい」、買収する側は「安く買いたい」と思うものだからこそ、双方が納得する譲渡価格に納めるため慎重に交渉しなければいけません。
交渉では情報の認識漏れや条件のすり合わせが立ち行かなくなる恐れもあるため、仲介会社の手も借りて慎重に交渉しましょう。
基本合意契約
譲渡条件や譲渡価格について交渉し、譲渡する方針が固まったら、基本合意契約に進みます。基本合意契約とは、譲渡条件について記した書類に署名押印することで、譲渡について合意する書類です。
あくまでも仮の契約ではありますが、基本合意契約からは譲渡を断る際に違約金(ペナルティ)等が発生することが基本のため、注意が必要です。
買収監査の実施
基本合意契約を済ませたら、買収監査(デューデリジェンス)を実施します。買収監査では、ノンネームシートや実地見学により定めた譲渡価格が適正であるか、運営実態や収益、クリニックの資産価値についてより詳細に監査できます。
このとき事前に通達されていた内容との相違があれば、基本合意契約も破棄できる場合がほとんどです。監査を誤ったり急いでしまい不備があれば、譲渡後にトラブルに発展する恐れがあるため、焦らずじっくりと進めましょう。
最終契約締結
買収監査にも問題がなければ、実際に最終契約を締結します。最終締結では監査をふまえた譲渡価格を提示し、双方合意すれば譲渡価格も契約を締結できます。
基本的には買収監査〜最終契約締結まで、1〜2ヶ月の期間を要します。同時に譲渡契約や不動産契約、行政や自治体への届出も必要なため、並行して進めましょう。
従業員への告知
最終締結が済んだら、クリニック譲渡は基本的には確定するため、譲渡が決まったことを従業員にも告知します。従業員は譲渡によりクリニックの経営者が変わることに不安を覚える恐れがあるため、譲渡内容はもちろん雇用契約において引き継がれることや変更が入る部分について、具体的に説明しておくことが大切です。
診療の引き継ぎ
告知が済んだら、実際にクリニックの運営において必要なことを引き継ぎます。業務内容や会計書類、患者のカルテなど運営に必要な内容を引き継ぎましょう。
クロージング後の引き継ぎ業務
クロージング後の引き継ぎ勤務として、以下の内容が必要です。
・スタッフへの業務引き継ぎや運営におけるヒアリング
・旧院長や退職するスタッフへの退職金の支払い
クロージング後の引き継ぎは、クリニックの譲渡内容によっても変わります。自分のケースではどのような業務が必要なのか、具体的に検討したうえで計画的にクリニック譲渡を進めましょう。
クリニック譲渡成立するまでの時間の具体例

クリニックを譲渡成立するまでの期間は、譲渡内容により大きく変わります。短い場合は4ヶ月程度、長い場合で3年以上かかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
クリニックを譲渡成立するまでの時間の具体例について解説します。
譲渡成立するまでの期間が短い場合
クリニックが譲渡成立するまでの期間は短い場合で4〜6ヶ月程度です。譲渡成立までの期間が短い場合として、以下が挙げられます。
・譲渡する側とされる側の条件や譲渡における要望が明確である
・譲渡する側とされる側の手続きや交渉の準備が整っている
・都市圏など収益性が見込める人気エリアのクリニックである
・患者が多く将来的な収益性が見込める条件が揃ったクリニックである
クリニック譲渡においてお互いが大切にしたいことが明確であったり、収益性が見込める条件が揃ったクリニックであれば、条件交渉もスムーズです。特にお互いにクリニック譲渡において柔軟に考えており、絶対に譲れない条件や収益性など、基本的な考え以外の部分ではさまざまな譲渡条件に対応できる場合は、短期間でクリニック譲渡を進められるでしょう。
譲渡成立するまでの期間が長い場合
譲渡成立までの期間が長い場合、2〜3年単位で交渉を進める必要があります。譲渡成立までの期間が長引くケースとして、以下をご覧ください。
・クリニック譲渡における条件や方針が固まっていない
・複雑な運営体制や珍しい診療科目を取り扱っている
クリニック譲渡における条件が明確に決まっていなければ、譲渡相手から条件について質問されてもすぐに答えられず、交渉が長引く恐れがあります。また運営体制や診療科目が複雑だと、譲渡を受ける側の継承に時間がかかる場合もあり、交渉や引き継ぎに膨大な時間がかかるでしょう。
クリニック譲渡に関するご質問や相談はMMCでできる
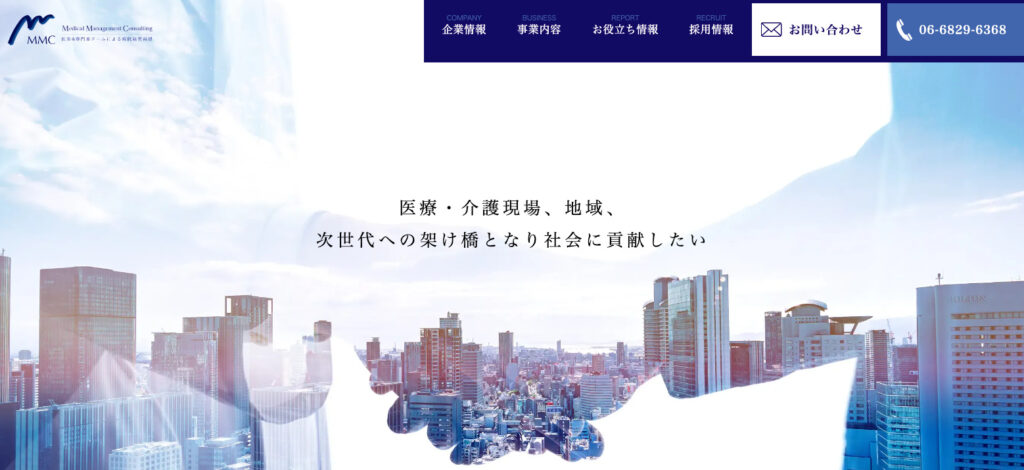
クリニックが譲渡成立する期間は4ヶ月〜3年以上と、ケースによって大幅な差があります。期間に差が生まれることには、条件交渉や手続きにかかる時間が大きく影響するため、スムーズにクリニック譲渡を進めるため、譲渡条件や運営方針について具体的に定めておくことが大切です。
MMCでは、クリニック譲渡やM&Aの仲介サポートを行っています。経営の立て直しから譲渡の仲介まで幅広く相談を承っているため、クリニック譲渡を検討している方は、ぜひお問い合わせください。